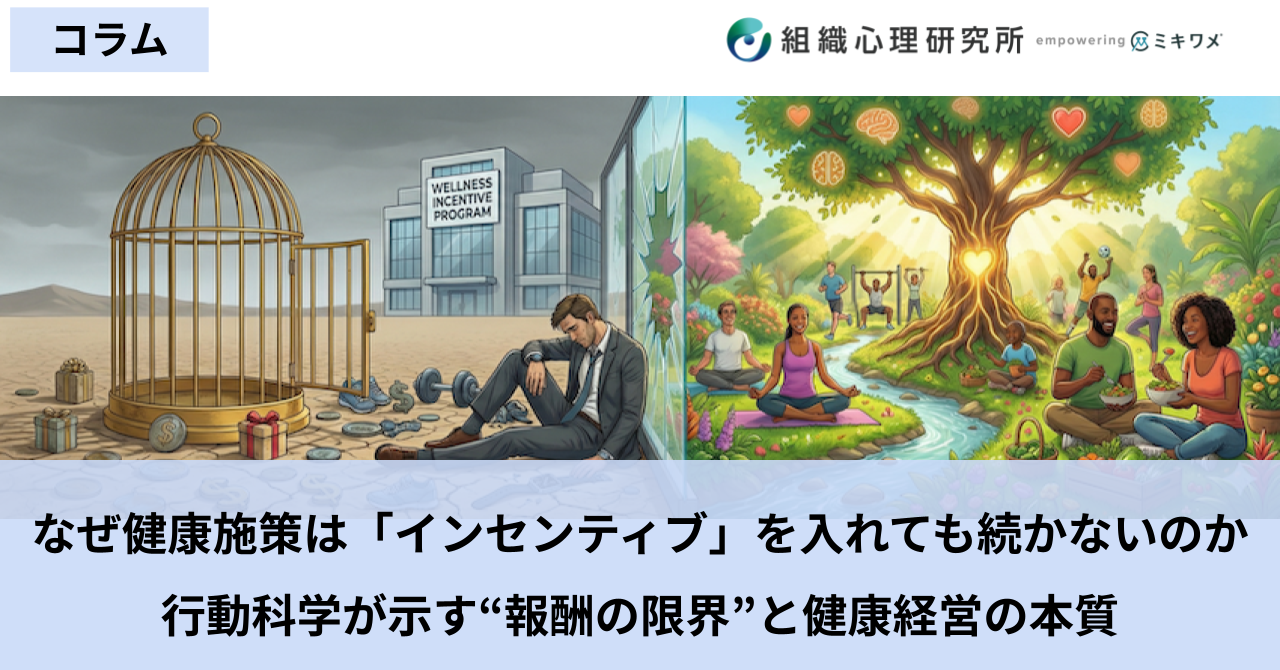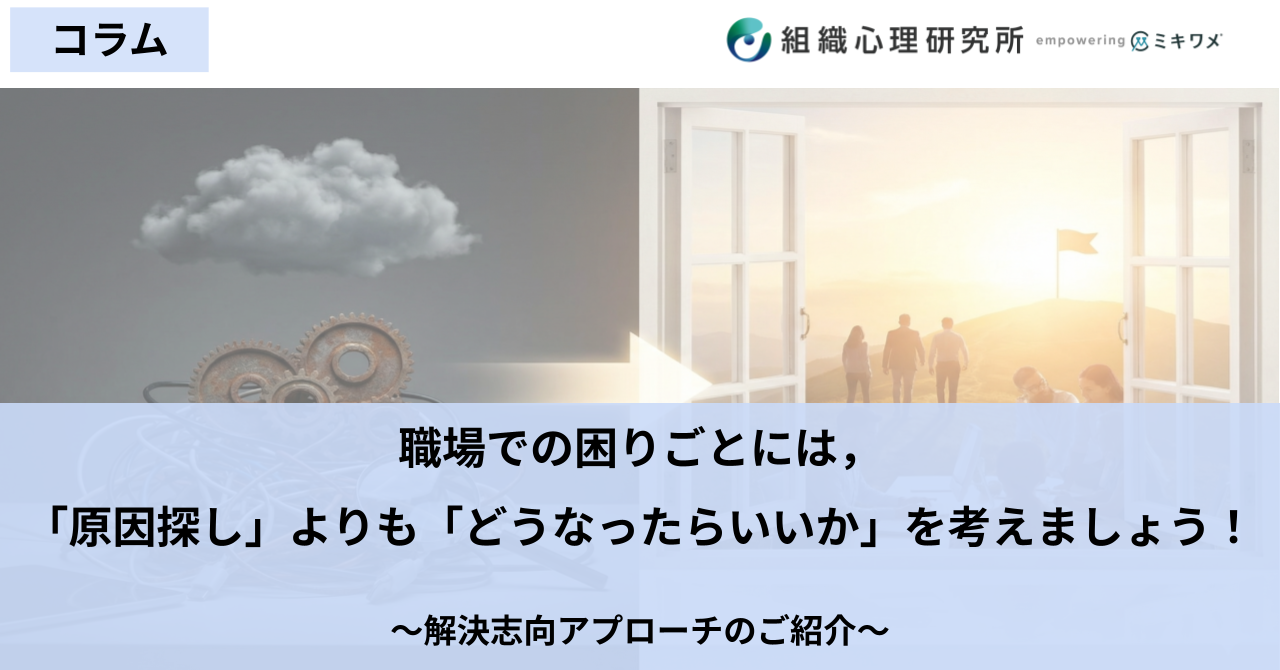本記事では、2024年9月26日に行われました、組織心理研究所主催セミナー第1回の内容をテキストでご提供します。
ゲストに、臨床心理士で精神科での実践経験や組織づくりの経験が豊富な坂井新先生をお招きし、以下のタイトルで講演いただきました。
「人的資本経営に潜む"幽霊"の心理臨床学 〜組織がコントロールできないモノとどう向き合うか〜」
以下に坂井先生のご講演内容を記事としてまとめなおしたものを掲載します。
1. はじめに
皆さん、こんにちは。今回のセミナー講師を務めます、臨床心理士の坂井 新と申します。私は新大阪にある精神科「とじまクリニック」で臨床心理士と副院長を兼任しながら、神戸の方では子どもから大人までを対象にしたセラピー・カウンセリングの場を立ち上げ、その代表をしております。以前は精神科病院で経営理事を務め、個人の心理療法と同時に組織全体をどう動かしていくかという経験も積んできました。
今回のセミナーでは、「人的資本経営に潜む“幽霊”の心理臨床学~組織がコントロールできないモノとどう向き合うか~」というタイトルを掲げています。ここで言う“幽霊”とは、必ずしもホラー的な存在を指しているわけではなく、「組織の中でどうしてもコントロールし切れない、人間の心や無意識の動き」を象徴するメタファーです。
私は長年、個人の治療・ケアと組織マネジメント両方に関わる中で、人間という存在の奥深さ、そして組織や集団としての心理的な動きに数多く出会ってきました。その経験を皆さんにお伝えしながら、一緒に考えていく機会になればと思っております。
2. 臨床心理士の仕事と「意識・無意識」の視点
まず、私の専門である臨床心理士や公認心理師という仕事が、一般的にどのようなものか紹介いたします。臨床心理士は、いわゆる「心の悩み」に対するカウンセリングや心理療法を行う専門家です。心理学のなかでも、特に「深層心理学」や「精神分析」といった学問的背景をふまえて、患者さんやクライエントと呼ばれる方々の「意識と無意識」の両面を捉えようとします。
普段、私たちは「意識的に考えて行動している」と思っていますが、一方で自分でも気づかない“無意識”の動きがあります。ちょっとした言い間違いや行動の失敗などが、その無意識を表すきっかけになるという考え方(失策行為など)は、精神分析を始めたフロイトによって知られるようになりました。
例えば、電車に乗っていて突然心臓がドキドキする、呼吸がままならないといったパニックを起こす方がいます。その人は「自分は元気なはず」と意識では思っていても、その裏にある無意識的なストレスや葛藤、人間関係の問題などが心身に影響している場合が多いのです。私は心理療法によって、そうした「無意識に潜む謎」にアプローチし、それを紐解く訓練を積んできました。そして個人の問題と同時に、組織全体を見立てる――つまり、人をまとめて動かす仕組みの背後にも「意識と無意識の力学がある」と考えています。
3. “幽霊”というメタファー
さて、今回のテーマである“幽霊”についてです。日本では病院や福祉施設など、人の生死に深く関わる場で「幽霊の噂」をよく耳にします。実際、私自身も病院勤務時代にスタッフから何度も「階段に見知らぬ人影が見えた」「夜中に廊下で誰かの足音がついてくるような感じがした」「院長室で誰かに声をかけられた」などの話を聴いてきました。
心理学的に見ると、「幽霊を見る」とは多くの場合、その人自身の死への恐怖や不安が投影されていると考えられます。病院という現場は、人が生きて退院していく場であると同時に、見取りの場でもある。さらに精神科病院では、心の病や障害によって“社会的に死んだ状態”に近いほど苦しい状況の方にも出会います。生と死の狭間にいるからこそ、人間の意識に隠れていた恐怖や不安と直面しやすく、それが幽霊体験として現れやすいのではないか――というわけです。
しかし近年、大病院化・システム化が進む医療の現場では、「幽霊を見た」「そんな話をする余地がある」という場が減ってきた印象があります。病院側がAIやバーコードなど徹底した管理システムを導入し、効率化が進むほど、患者とスタッフの関わりは機械的になり、人間的な触れ合いが希薄になる。すると“幽霊を見る”という曖昧な心の動きが語られなくなるわけです。ここでは「幽霊=曖昧なもの」を受けとめる余白が失われているのかもしれません。
4. 病院の管理体制とマニュアル化の影響
私がある大病院に入院したときの実体験からも、この「管理体制と人間的関わりの対立」を強く意識しました。入院患者にはバーコード入りのリストバンドが付けられ、看護師や医師とのコミュニケーションも最小限。人為的ミスを減らすためには合理的かもしれませんが、患者としては自分が“一体どこで、誰に、何をしてもらっているのか”がわかりづらく、ちょっとした質問さえもままならず、とても孤独に感じました。
こうしたシステム化・マニュアル化は、もちろん医療事故やエラーの低減には役立ちます。しかし、人間同士の関わりを「非効率なもの」として排除していくほど、生と死を含めた人間の奥深い部分(無意識や情緒面)に触れる場は狭まっていきます。結果として、「幽霊(曖昧なもの)」や、死と向き合う機会が薄れてしまうのではないか――これが私の問題意識の出発点です。
5. 3つの事例(マニュアルの功罪)
5-1. 東日本大震災:大川小学校の悲劇
私が長く支援に関わっている東日本大震災の現場から、まず大川小学校の事例を紹介します。ここでは津波が“まさかそこまで川をさかのぼってくるとは想定していなかった”ため、学校側が「運動場へ集合する」というマニュアルに従い、避難を遅らせてしまい多くの児童・教員が犠牲になりました。
一方、「先生の指示に従わず、裏山へ逃げた児童たち」は助かっています。これは単純に「マニュアルが悪」という話ではなく、“マニュアルを使う・使わない”という瞬間の判断が、生死を分ける状況となった悲劇でもあります。万全だと思われたマニュアルが、想定外の現実に対応できない危うさを示す一例です。
5-2. 同じ地域の海岸線パルプ工場:マニュアルが奏功したケース
同じ石巻の海岸沿いにあるパルプ工場では、昔から「大津波は高台の日和山へ逃げる」というローカルルールが語り継がれており、それをもとに社内マニュアルを整備していました。津波の当日、工場の多くの方々はそのマニュアルどおり日和山へ避難し、生き残ったのです。
ここではマニュアルが非常に有効に機能したわけで、大川小学校と対照的です。マニュアルが持つ可能性と限界、両面を考えさせられる対比的な例といえます。
5-3. 災害が連続する病院経営の現場:コロナ禍でのマニュアルをめぐる葛藤
私が以前いた精神科病院では、台風や地震などが立て続けに起こった後、コロナ禍を迎えました。ここで起こったのは、スタッフそれぞれが置かれた立場と「病院としての使命」の間で生まれる衝突です。
• 「患者さんよりも自分が感染するリスクを恐れて出勤を控えたい」という人
• 「マスクやワクチン費用は病院が負担すべきだ」と訴える人
• 「患者さんを守るためなら缶詰め状態でも働く」と自ら申し出る人
スタッフ個々で姿勢が分かれ、さらにワクチン接種を巡って部署間でトラブルも起こりました。みんな、国のガイドラインや組織のマニュアルに従おうとしますが、日々状況が変わる中で「どこまでそれを“守るべき絶対”とするのか」悩む場面が出てくるわけです。
こうしたとき私は、トップダウンで指示を押しつけるのではなく、「各部署が自分たちで現実に合ったマニュアルを考え、院内で共有しよう」と提案しました。結果、すべての部署が試行錯誤しながら独自のルールを作成・更新していくことで、“守るためのマニュアル”ではなく“考えるきっかけとしてのマニュアル”が生まれました。
6. 三方よしの経営・組織づくりと“幽霊”を生かす場
大阪には昔から「三方よし」という商売哲学があります。売り手・買い手・世間(社会)の三方が、それぞれうまくいく落としどころを探り合う考え方です。病院でいえば「治療者・患者・病院経営」三者すべてにとってよりよい形を模索する、という意味になります。三方の視点を持つことで初めて、組織は一面的な効率化に偏らず、人間的な関係や曖昧さを受け入れる余地を残せるのではないでしょうか。
曖昧なものはときに“幽霊”のように不確かで、組織が管理しづらい存在かもしれません。しかし、それを排除してしまえば、私たちの内外に潜む無意識や情緒、関係性の深みは失われていきます。結局、意図的に人が出会い、話し合い、「何のためにこのシステムやマニュアルを使うのか」を共有する“場”が必要です。そして、その“場”を大事にし続けることこそ、人的資本にとっての「持続的な力」になると私は考えています。
質疑応答
Q1: 在宅勤務・フリーアドレス化で繋がりが薄れたと感じる。心の問題は増える?
質問 在宅勤務やフリーアドレス制の導入によって、チーム内の繋がりが薄れているように感じています。一方、在宅勤務は働きやすさにも繋がるため続けてほしい制度でもあります。こうした状況で心の問題が増えたりする例はありますか? また、直接会う回数が少なくても、関係を良好に保つためにできることがあれば教えてください。
回答(坂井) 実際に「在宅勤務で気持ちが楽になった」という方もいますが、「対面の関わりが激減して孤立感が増した」と感じる方も多いです。それは個々の特質にも左右されます。対面コミュニケーションが好きでモチベーションになる人にとっては、在宅勤務が長引くほどストレスになる場合があります。
一方で、今ではオンラインでも一定の関係性・やりとりは可能です。物理的に触れ合うのとは違った“良さ”や“深まり”もあり得ます。ただし、意図的にフェイス・トゥ・フェイスの場をつくる、月に一度は直に会って話す時間を確保するなど、オンラインとオフラインのバランスを意識的に設計するのが望ましいでしょう。さらに重要なのは、「どうしてこの働き方(マニュアル・ルール)を導入したのか」「自分たちは何のためにツールを使っているのか」を明確に共有し続けること。繋がり方の方法が変わったとしても、みんなで方針や狙いを話し合いながら調整する姿勢があれば、心のトラブルは起きにくくなります。
Q2: 価値観が多様で温度差があるスタッフ/部署を巻き込むコツは?
質問 事業会社だと「患者を助ける」というような明確な軸があるわけではなく、各人がそれぞれ違う目標や働く動機を持っています。温度差が生じるなかで、一緒にマニュアルを作ろうにも「面倒」「関わりたくない」という人が増えてきてしまう。そういった環境で、どう巻き込みを図ればよいのでしょうか?
回答(坂井) 確かに多様な人が集まると、摩擦が増えやすいです。しかし大切なのは、摩擦を“避ける”のではなく、生産的な議論に変えていくこと。そのためには「自分は何を考えているのか」「自分は何をしているのか」を、きちんと説明し合うのが第一歩だと思います。案外そこを省いて「どうせ分かってくれない」と思いこんでしまいがちです。
また、「どういう部分なら共同で作業できるのか」を少しずつ探っていくことも効果的です。絶対に合意しなくてはいけない“最終ゴール”をいきなり決めるのではなく、小さな合意と関わりの経験を積み重ねていくことで巻き込みやすくなるはずです。
Q3: DXやマニュアル化は大事だが、曖昧さも残したほうがいい?
質問 組織として生産性や効率化を高めるために、DX(デジタルトランスフォーメーション)やマニュアル化を進めるメリットは大きいと実感しています。一方、組織風土やエンゲージメント維持のためには、人同士が曖昧な部分を共有し合う機会も必要なのではないか、と今回のお話を聞いて感じました。曖昧さを許容する姿勢とは、具体的にどのように考えればいいのでしょうか?
回答(坂井) 私もマニュアルを否定しているわけではありません。マニュアルがあるからこそ、ミスが減り、誰がやっても最低限の質が保たれる。効率化の恩恵は大きいです。ただ、それを「守ること」自体が目的化すると、本来の目的や背景(なぜ作ったか? 何に使うか?)が忘れられます。曖昧さを許容するというのは、「マニュアルに収まらない想定外の出来事が必ず起こりうる」ことを前提にしておく、ということです。そのときに“答えのないやりとり”が生まれる場を残しておく。マニュアルが整備されればされるほど、その“余白”をあえてつくることが大切です。
Q4: 「作る過程が重要」というのはどう理解すればよい?
質問 講演で、「マニュアルは作って終わりではなく、作る過程で関わることが大切」とおっしゃっていました。これは「マニュアルを一緒に作る過程そのものが、人と人の繋がりを強化する」という解釈で合っていますか?
回答(坂井) はい、私の考えではそのとおりです。組織やチームでマニュアルを整備するとき、一番大事なのは「どういう目的で、どんな基準を設けるのか」を一人ひとりが考え、それをすり合わせていくことです。そこでは必ずコミュニケーションが生まれ、意見の衝突もあるかもしれません。そうした“プロセス”こそが、組織にとって生きた学習や連帯感を生み出します。一方で、完成したマニュアルを「ただ守りましょう」と押し付けてしまうと、関係性の深化が起こりにくくなり、むしろ人間的な部分が遠ざかってしまう可能性があります。
おわりに
「人的資本経営に潜む“幽霊”」というやや奇抜なタイトルではありますが、本質的には“人間の心や無意識の動きをどこまで意識的に扱うか”という問いです。私たちは往々にして、曖昧で扱いづらいものをマニュアルや制度で排除し、効率を上げようとします。それ自体が悪いわけではありませんが、“幽霊”と呼べるようなコントロール不能な動きこそ、人間や組織の奥深さを保ち、創造性をもたらす源にもなります。
組織においては、「幽霊なんていない」と割り切るのではなく、むしろ「どこかにいるかもしれない」と心に留めおくことが大切なのかもしれません。あえて意図的に人が出会い、話し合い、摩擦を恐れずに意見を出し合う場をつくる。そうした関わりこそが、今後の組織づくりや人的資本経営を支える大きな要素になるのではないでしょうか。
ご質問やご意見がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。私が運営する神戸のケア拠点でもオンライン相談を行っております。下記にHPなど掲載しておきますので、今後もさまざまなテーマでお話や議論ができれば嬉しく思います。本セミナーで少しでも気づきやヒントを得ていただければ幸いです。最後までお読みいただき、どうもありがとうございました。
メイン講師:坂井 新(さかい あらた)
臨床心理士・公認心理師、とじまクリニック副院長、(株)epifunny company代表取締役
京都大学大学院教育学研究科 博士後期課程(研究指導認定退学)。児童養護施設生駒学園、兵庫県精神科救急窓口、兵庫県災害復興総合センター、(医)北斗会さわ病院、(医)遊心会にじクリニック副院長、京都大学・相愛大学非常勤講師などを経て、現職。
主に子どもや精神疾患、精神保健福祉、災害支援などの分野から、幅広く専門的な心理支援(心理療法や心理アセスメント等)を実践し、現場での後進の指導教育や、精神医療、精神保健福祉の組織マネジメントに携わる。
著書:『ライフステージを臨床的に理解する心理アセスメント(共著)』(2020年、金子書房),『精神分析臨床での失敗から学ぶーその実践プロセスと中断ケースの検討(共著)』(2021年、金剛出版)など。
<株式会社epifunny companyについて>
坂井は、実際にクリニックの副院長という管理職という立場もありますが、長年の臨床実践において、病院では相談が叶わない人たちもたくさんいるという経験をしてきました。
例えば、別に病気ではないけど夫婦関係について相談したいけど、、、自分の子どもの様子が最近きになるけど、病気といった症状があるわけではないので、病院では診てもらえない。という医療と現実のエアポケットにはまり込んでしまう人たち。こうした人たちは実際どこにいけばいいのか?それがなかなか見いだせないのが現実なのです。そうした人たち、子どもから大人まで、なんらかの形で相談やケアを提供できる場所が必要ではないか?という考えのもと、仲間と一緒に設立された会社です。
<Therapy Plays epifunnyについて>
病院での治療を受けることが目的でなく、その人にとって本当に必要な”かかわり”を通じて、気兼ねなく相談ができ、一緒に思い悩みことができる場がTherapy Plays epifunnyです。
その中でもPsychoTherapy Cabinetは、基本的に成人の相談をお受けする場所です。自分に関わる悩みを相談する心理カウンセリング、子どものことについての親相談、そして自分を洞察的に見つめなおし発展的に考えるための手法として、より専門的な精神分析的心理療法などを提供しています。
この場の中核であるTherapy Plays epifunnyでは、子どもたちへのケアやセラピーを、個別・集団ともに提供しております。私たちの考えるケアやセラピーは、子ども本人の主体性をのびのびと成長させるようにすること。それを反映させるための場所と人の関わりという両者の混ざりあいが必要と考えております。ですので、人との関わりを濃い個別プレイセラピーから、人と空間から反映する力を利用するグループセラピーやワークを実施しています。
このような場になるためには、ある意味特殊な空間を必要とすると考えています。この考えを反映させた新しい空間はHPやSNSにて紹介もしておりますので、下記にHPやSNSを記載していますので、実際にアクセスして、この目で見てご覧いただけますと幸いです。
今回講演では組織臨床について話しました。会社組織の中での人間関係の困りごとについて、こんなことを相談してもいいのかな?と思うようなことでも構いません。まずは遠慮なくご相談ください。一回きりでその後の指針が開ける場合もありますし、継続してみるからこそ見えてくるものもございます。ご自身だけでなくご家族の相談等まで幅広く対応しています。オンラインでもお受けできる場合もありますので、お気軽にご相談ください。




【HP】https://epifunnycompany.wixsite.com/therapy-plays-epifun
【Instagram】http://www.instagram.com/therapy_plays_epifunny?
司会・話題提供:佐藤 映(さとう うつる)
臨床心理士・公認心理師、株式会社リーディングマーク 専門役員/組織心理研究所 所長
京都大学大学院教育学研究科博士後期課程(研究指導認定退学)
大阪府出身。京都大学および同大学院で学び、大学教員を経て、現在は経営者や人事に向けて、心理学を活用した支援や研究を行っている。サーベイや適性検査を用いた組織分析やコンサルティングで150社以上を支援。
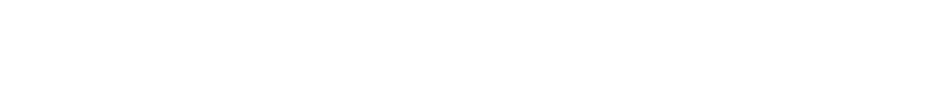
.png&w=3840&q=75)